<活用編 6> 子どもを対象としたOPIテストの活用法 (2000年2月号)
中島 和子
| OPIの活用編として、OPIテストが実際に日本語教育機関でどのように利用されているのかを紹介しています。今月はその6回目。子どもを対象としたOPIテストの活用法を取り上げます。 |
はじめに
会話力を伸ばすこと、その伸びを的確に把握する測定ツールが必要なことは、子どもの日本語教育でも変わりはない。むしろ、子どもはいろいろな面で発達途上にあるだけに、そのニーズがより高いといえよう。
ACTFL-OPIテストは、学習者の口頭能力を全体的・統合的に捉え、一定の基準に照らし合わせて評価しようとするものであり、子どもの会話力の評価にも役立つものである。しかし、もともとOPIテストは、一つの言葉(母語)がすでに形成されたモノリンガルの大学生・成人のために考案されたものであるだけに、母語も外国語も両方とも発達途上にある言語形成期(12、13歳まで)の年少者に使用する場合には、特別な配慮が必要である。
子どもの会話力を知りたいとき
子どもの場合、どのようなときに会話力を調べ、評価する必要があるのだろうか。成人・大学生と同様、まず「学級編成(Placement Test)」、「会話シラバス設定(到達目標)」、「授業の会話指導の手段」、「語学プログラムの診断・評価」のために必要であることは言うまでもない。これらに加え、次に示すような状況で口頭能力評価が必要とされている。これらは子ども特有のニーズといえよう。
(1)教科学習との関係
成人・大学生の場合、外国語を使ってどんなタスクがこなせるかというと、仕事上で難しい交渉ができる、相手を説得できる、裏付けのある仮説が述べられる、自説を弁護できる、などが目標として掲げられる。子どもの場合、それらに相当するタスク遂行能力は何かというと、外国語を使って年齢相応の算数、理科、社会などの教科学習ができるかどうかということであろう。つまり、外国語が、考えるツールとして、また知識獲得のツールとして、どのくらい使いこなせるかということである。
近年、子ども対象の日本語の学習は多様化し、教科学習との関連で行われる形態が多くなっている。例えば、イマージョン方式の日本語プログラムがその一例である。イマージョン方式とは教科学習の道具として外国語を使用することによって、学齢期の間に高度の外国語力を育てようとする試みである。これは人為的に教科学習と組み合わせて外国語を教える場合であるが、最近、日本の公立小・中学校で受け入れている外国人子女の場合は、個人選択の余地なく、教科学習が押しつけられる、いわゆるサブマージョン方式である。
また、海外に散在する補習校などにおいても、長期滞在の子どもや国際結婚の家庭で育つ二文化児が増え、日本の教科書を使用した学習に耐えるだけの日本語会話力があるかどうかを判定するツールを必要としている。
つまり、各教科の授業についていけるだけの日本語の会話力がどの程度まであるかを判定し、また、そのような力を培うのが日本語教師の大事な仕事になりつつあるということである。そのためには、簡便で子どもに適した会話テストを必要としており、もしACTFL-OPIをこのような目的のために使用するなら、意図的に教科学習と関連したトピックやテーマを加える必要がある。
(2)母語との関係
言語形成期の子どもは、母語の話し言葉が固まるのが大体8歳前後、具体的思考から抽象的思考に移行していくのが10歳前後といわれる。当然のことながら、この間の外国語学習は母語の発達度の影響を受ける。したがって、母語でできないことは外国語でもできないと思うべきである。外国語の会話力テストも、母語の発達度を十分考慮して行わなければならない。例えば、外国語で複雑な構文(文法)を駆使して段落構成(談話の型)がきちんとできるようになるのは10歳以降であるし、社会性がかなり発達していないと、ひねくれた状況を処理できる(機能・タスク)力も期待できないのである。
また子どもの置かれた言語環境によっては、母語と外国語の2言語の分化がはっきりしない場合もある。特に学校と家庭で言葉を使い分けて育つ日系子女・外国人子女などの場合は、いろいろな形の2言語の混用が習慣化されることが多い。ACTFL-OPIでは、日本語で応答をしている途中で、母語の単語などを使ったりすると、外国語の力の限界のために母語単語を使用したと捉え、一律に「挫折」の証拠と捉えがちである。しかし、子どもの場合は、あながち「挫折」として扱えない場合も出てくるということである。
家庭で、親は日本語、子どもは英語というような言語習慣が身についてしまっている子どももあり、日本語を聞いて理解はするが話すのは現地語のみという、聴解力と発話力が極端にアンバランスなケースもある。
しかし、多言語環境で育つ子どもの中でもっとも質の高い会話テストを必要としているのは、何といっても、「2言語低迷型」のバイリンガルであろう。両言語を一応話すが、どちらの言葉も認知面において年齢相当のレベルまで達しておらず、そのために学習困難に陥るケースである。このような弱い読み書き能力を放置せず、予測性の高い口頭能力テストによって、このような子どもを早期に発見し、適切な処置をとりたいものである。
子どもの会話テスト
このようなニーズにもかかわらず、子ども用の会話テストは未開発の分野である。これまでに開発されたものとしては、わずか日本語イマージョンブログラムのために必要に迫られて使われた諸テストと、カナダ日本語教育振興会が開発してきた多言語環境に育つ子どもを対象とした会話テストぐらいのものである。いずれもACTFL-OPIを土台にして、子ども用に改良、発展させたものである。
(1)COPE日本語版とSOPA日本語版
ワシントンD.C.のCenter for Applied Linguistics(CAL)がイマージョン教育用に開発(1988)したのがCAL 0ral Profciency Exam(COPE)で、2人の子どもをペアにして行う面接テスト(15~20分)である。ロールプレイとディス力ッションを通して、対話面(social language)と教科学習面(社会、地理、理科)を調べ、ACTFL-OPIの査定基準を使って、理解、流暢度、語彙、文法の4面から評価している。
Spanish 0ral Profciency Assessment(SOPA)も同じくCALが開発したスペイン語用(1~4年生)に開発したテストである(日本語訳1995)。色つきのプラモデルの果物や動物を袋から出して、テスターが簡単な指示を与え、それに応じる聴解力、インフォーマルなQ&A(例:家族のメンバーの年齢)、理科(例:植物の一生)、物語再生(例:ゴディロックと三匹の熊)などで構成されている。
(2)0raI Proficiency Assessment for Bilingual Children(OBC)[注]
2言語に触れて育つ子どもの会話力を、絵力ードを使用して3面(言語面・対話面・認知面)で捉えようとする、約10分の個人面接テスト。右下の図のように、導入会話でレベルチェックをし、基礎タスクに進むか、対話タスクに進むかを決め、さらに対話タスクから認知タスクに進むか、対話タスクで終了するかの選択肢がある。
絵力ードは、例えば、スポーツ力ード(基礎タスク)は図のようなものであり、これを使ってテスターが「 」のような質問をし、それぞれ【 】に対する反応を見るわけである。
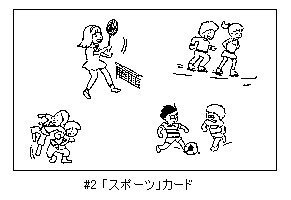
| ・「~ができますか」 【可能表現】 ・「どんなスポーツが好きですか」【好き嫌い】 ・「サッカーをしたことがありますか」【過去の経験】 ・「~と~と、どっちのほうが好きですか」【比較表現】 |
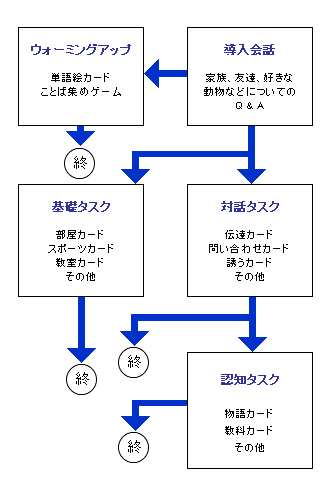
このように、OBCは子どもの年齢差と言語環境差で、タスクの質・量の調整ができるように考案されている。例えば、幼児や小学校1年生は、一部の例外を除いては、導入会話と語彙テストや言葉集めなどのゲームのみ。外国語として日本語を学習する低学年の子どもの場合は基礎タスクまで、しかし、高学年は対話タスクの一部までこなせる可能性がある。教室外で日本語を使用している子どもの場合は、基礎タスク抜きで導入会話から対話タスクに進む。さらに日本語で教科学習をしているイマージョンプログラムの子どもや外国人子女の場合は、対話タスクから認知タスクに行き、各種の教科カード(例:理科なら「公害」「地震」のカード)をこなす。しかし、教科学習をしていない日系子女などの場合は、認知タスクの中でも、教科とはあまり関係のない「物語の再生」まででやめる、という具合である。
ACTFL-OPIを子どもに使用する際の注意
ACTFL-OPIをそのまま子どもに使用する場合には、つぎのような点に留意すべきであろう。
まず子どもの年齢を考慮し、低学年の場合は10分ぐらいが体力・集中力の限界と考えたほうがよい。また読み書き能力の発達度によって、ロールカードの文字が読めない、読めても意味が理解できないことがあるので、絵だけで状況がわかる文字なし絵力ードを用意する必要があろう。
ロールプレイそのものは子どもの遊びの一部であり、子どもに適したアクティビティーといえるが、テスターの要求で子どもがその気になるかというと別問題である。低学年の場合はなるべくロールプレイを避け、子ども自身に関する自然体のQ&Aが望ましい。
子どもは面接テストの目的や効用を理解しないから、気分が向かなければ、話にのってこない。また自信のない言葉になると「わからない」、「知らない」を連発して、テスターを困らせることもある。親が「おしゃべりで、話しだしたらとまらないんですよ」という子が、面接テストではだんまり屋、ということがよくあるのである。このため、大人とは違った心理的配慮をし、子どもが話しやすい雰囲気づくりをする必要がある。例えば、SOPAの色つきプラスティックの動物や果物は非常に効果的だし、またOBCのウォーミングアップ用のゲームや語彙テストも子どもの気持ちをほぐすのに役立っている。
またこれと関連して、ACTFL-OPIの評価で中心的役割をしている「突き上げ」は子どもには問題があり、力以上のことを無理に言わせようとすると、一切口を開かなくなるということもある。子どもには過度の「突き上げ」は避けるべきであろう。
評価面での注意
評価面では、どのレベルを上限と考えるべきであろうか。子どもの場合、高度の漢語系語彙の使用や、敬語使用、連段落の一人話は当然期待できないから、「上級の下」ぐらいを上限として、全体を3段階ぐらいに評価するのが適当であろう。
子どもの会話力の評価でいちばん難しいのは、何といっても性格との関係である。積極性がなく発話量が極端に少なく、会話参加態度が悪い場合に、それが会話力が低いためなのか、もともと内向的な性格であるためそうなのか、判断に苦しむことが多い。子どもが非常に優れているのは「発音」で、母語の影響をあまり受けないようである。
会話テストを子ども自身がどう見るかというと、たとえ片言であっても、またどんなに不出来であっても「日本語が話せた」と思うのが普通で、それが励みになって学習意欲につながるケースが多い。テストを前向きの経験にすると同時に、定期的に繰り返すことに教育的意味があるのである。
〔なかじま かずこ〕-トロント大学
| [参考文献] Rhodes,N. & Thompson,L.1990. An oral assessment instrument for immersion students:COPE. ln A.M.Padilla, H.H.Fairchild, & C.Valades(eds.) Foreign language education; Issues and strategies. pp.75‐94. Newbury Park,CA:Sage. [注] カナダ日本語教育振興会 (2000) 『子供の会話力の見方と評価:OBC』 |

